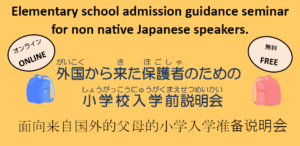1.イベント「西東京市日本語スピーチコンテスト2025」
西東京市に在住、在勤、在学の外国につながりのある方々が、日本語でスピーチを披露します。スピーチの内容は、日本での生活で感じたことや考えたこと、母国への思い、西東京市とのつながりなど、多岐にわたります。このイベントは日本語やスピーチの上手さを競うものではありません。交流パーティーも開催いたしますので、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
日時 10月5日(日) 午後1時〜4時
交流パーティー 午後4時〜(40分程度)
会場 J:COMコール田無 多目的ホール 入場無料(予約不要)
共催 西東京市
問い合わせ 西東京市多文化共生センター
TEL:042-461-0381 Email:info@nimic.jp
西東京市生活文化スポーツ部文化振興課
TEL:042-420-2817
2.募集「『西東京市日本語スピーチコンテスト2025』当日ボランティア」
受付、会場設営、交流パーティ準備等、当日の運営をサポートするボランティアスタッフをNIMIC会員から募集します。スピーチを楽しみながら運営に参加しませんか。初めてのご参加大歓迎!ぜひご協力をお願いします。
募集人数 5名
日時 10月5日(日)午前11時集合、午後5時解散予定
応募 9月12日(金)までに、 info@nimic.jp 宛へメール(件名:スピコンボランティア)でお申し込みください。
※9月17日(水)午後4時40分-6時00分、コール田無4F(会議室B)で、当日ボランティアと実行委員の顔合わせミーティングを行い、当日の流れや役割分担について説明します。
欠席の方は、個別に説明をしますのでご相談ください。
3.「武蔵野大学夏季研修日本文化体験」終了報告
7月31日および8月2日に地元の武蔵野大学からの業務委託で夏季日本語留学生41名に対し日本文化体験を行いました。延べ41名の協力者を得て、和菓子とお点前、姉様人形作り、書道、および浴衣を着て「たてもの園」見学と散策を実施しました。留学生は自分が作った和菓子を食べて抹茶をいただき、説明を聞いた江戸時代の農家の前で浴衣姿の写真を撮り、大好評でした。今回は3回目の文化体験で準備も実施も余裕を持ってできました。
4. 「親子であそぼう 多言語で楽しく!」終了報告
8月24日(日)きらっとにて「親子であそぼう 多言語で楽しく!」を開催しました。オランダ語(英語混合)・韓国語・ロシア語・タイ語で、各国の伝統的なゲームや踊り等を体験し、親子共に新鮮な言語と文化の出会いを4カ国を旅するように次から次へと楽しみました。参加人数は親子合わせて19人、講師・サポーター・スタッフは今年度からの新しい「遊ぶ」がテーマのプログラムの楽しさに手応えを感じました。次回も参加者を増やすのが課題です。
5. 講演会「北欧の図書館から学ぶ市民と図書館とは…」
長年、北欧の図書館を研究してきた講師が、現地の図書館の考え方や建築、市民の様子を美しい映像を交えて紹介します。図書館の魅力を再発見するためのヒントが見つかるかもしれません。
日時:10月4日(土)午後2時~4時(受付1:45~)
会場:柳沢公民館視聴覚室(定員70人 申込先着順)
講師:吉田右子氏(筑波大学図書館情報メディア系教授、北欧の図書館に関する図書多数))
参加申込(無料):9/2からフォームで。 https://forms.gle/SY6fzyCShJrJgamW8
共催:西東京・図書館と歩む会、西東京市公民館(市民企画事業)
※市内公共施設配布のチラシをご覧ください。
6.エッセイ:ラオスへの旅(5)ルアンパバーン 朝の托鉢1
ルアンパバーンのホテル一夜目、村上春樹のエッセーを読んで以来、ここでの一番したいこと「托鉢」に参加することになった。朝の托鉢(タクバーン)はラオス仏教の重要な儀式ということで、早朝に行われる。ラオス国民の大多数が敬虔な仏教徒であるため、朝の托鉢は日課の一部になっているそう、日本人の仏教感とは全く異なるようだ。
娘たちがホテルに托鉢のための籠やお供物を準備してもらい、明け方5時に起床、まだ庭園の中のコテージは寝静まっているようで気温は15度くらいで気持ち良い。
「ホテルの前の通りに出てみない?」とMina、ホテルのフロントに行くとフロントマンが通りにゴザを敷いてその上に小さな椅子を準備してくれた。周りには住民がゴザに畏まって托鉢の行列を待っている。
そして朝の通りをオレンジ色の衣を着た托鉢の僧侶たちが静かに私たちの前に進んでくる。まるで幻想の中に存在するかのようだ。
(佐々木瑞枝)
7.Book:絵本『シリアの秘密の図書館』 ワファー・タルノーフスカ作
ヴァリ・ミンツィ絵 原田 勝 訳 くもん出版 2025年5月
内戦下のシリア。戦闘が広がり、その町でも砲弾が飛び交うようになり、建物が瓦礫の山になって中にあったものが通りにばらまかれていました。人々は毎晩地下室に集まっては停電の夜を過ごしました。食べ物を分け合ったり、懐中電灯の光で本を読んだり、トランプをしたり…。攻撃が少しおさまる昼間、家に帰ったり買い物したりするのですが、子どもたちは道に散らばっている本を拾い集めるようになり、使われていない広い地下室を見つけて、たくさんの本を運び込みました。この子どもたちの始めた地下図書館は口コミで広まり、大勢の人々が利用するようになりました。「この図書館のおかげで、子どもたちは希望を持ち、暗い破壊の時期を、明るく新しい夜明けにむかって進むことができたのでした。」とのこと。内戦下ダラヤで実際にあった話と著者の体験から描かれた本です。
シリアはユーフラテス川の流域、古代文明が栄えた地で、様々な人々・言語・文明・宗教の入り混じった土地で、紀元前7世紀には世界最大の図書館があったそうです。巻末資料に長い歴史を感じました。
(NIMIC会員 根本百合)
メール配信の申し込みは、こちらから