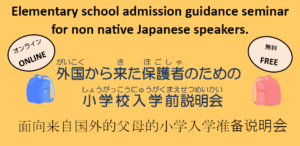1.外国人の参加者を募集「市内歴史ウォーキングで交流会」
市内の石神井川を歩いて東伏見稲荷神社と下野谷遺跡を訪ねます。外国人参加者、日本人スタッフ、みんなが交流するイベントです。
日時: 11月15日(土)13:30~16:00 (雨のときは中止)
集合: 西武新宿線の東伏見駅南口階段下
対象: 西東京市で、住んでいる・働いている・学んでいる外国人
小学生は保護者といっしょに参加すること
定員: 20人くらい
費用: 一人100円(保険料と交流会費)
通訳: 英語、中国語、韓国語
申込み:「名前、住所、電話番号、メールアドレス、母国語、通訳が必要または不要」を書いて11月2日(日)までにメールで。タイトルは「ウォーキング」。
申込み・問合せアドレス: info★nimic.jp (★を@にしてください)
くわしいことは多言語チラシをどうぞ。
https://nimic.jp/wp-content/uploads/2025/09/History-Walking2025.pdf
皆さんのお知り合いの外国人の方々にご案内をお願いします。
2.西東京市民まつり・NIMICブースに大集合!
NIMICは多文化共生の地域づくりを目指し、その活動の広報のために、第22回西東京市民まつりに出展します。
NIMICブースでは、ポスター展示での活動紹介やクイズ等をする予定です。
市民まつりに来場し、他の市民団体の展示や活動を楽しみつつNIMICブースに立ち寄ってください。日頃あまり会う機会のない会員とも交流できる良い機会です。
NIMIC ブース番号は、146番で会場正面入口から一番右側(北側)の通路の奥付近です。
当日は緑色のぼり旗を目印においでください。皆さんのお越しをお待ちしています。
市民まつり日時:11月8日(土)午前10時-午後4時、9日(日)午前9時-午後3時30分
会場: 西東京いこいの森公園(緑町3丁目)
3.募集「西東京市民まつりNIMICブースの当日ボランティア」
上記のイベントの当日ボランティアを、NIMIC会員から募集します。準備、片づけ、ブースでの説明やクイズ対応などが仕事です。午前または午後の数時間でもOKです。午前と午後の通しで協力される方には昼食を用意します。
当日ボランティア日時:11月8日(土)午前9時-午後4時、9日(日)午前9時-午後4時
申込み:メールタイトルは「市民まつり当日ボラ」、参加できる日時を書いて、 info★nimic.jp まで(★を@にしてください)。
皆さまのご参加、ご協力をお待ちしています。
4.「西東京市日本語スピーチコンテスト2025」終了報告
10月5日(日)に表記のイベントを開催しました。
発表者9名、子ども日本語教室の小中学生3名のメッセージと、市民審査員5名、特別審査員3名の参加があり、会場には90名近い観覧者が来場されました。
市長賞は、ミャンマー出身のピョピョカイさん、武蔵野大学学長賞は、モンゴル出身のダシニャム シャダウさん、NIMIC賞は、インドネシア出身のアンドレ アディティヤさんが受賞されました。
コンテスト終了後の交流会も70名の参加があり、コンテストと共にとても和やかな会となりました。観覧者のアンケートでは、チャレンジ精神に勇気をもらった、多文化共生を考える良い機会となったなどのコメントをいただき実行委員としてとてもうれしく感じています。
5.研修会:高校での日本語教育に関心のある皆さまへ
(専門家相談会などを開催しているCINGAからのお知らせです)
日本語指導を必要とする高校生は年々増加し、都立高校でも日本語教育が展開されています。
一方で、校内ではどのような仕組みで、どのような教育活動が行われているのか、その実際を知る機会があまりありませんでした。
本研修会では、日本語教師の方を対象に、「高校での日本語教育」を学び合う機会をつくります。
〇第1回目 「東京都内の公立高校における日本語教育の制度と実際」
日 程 11月9日 (日) 10:00~12:00
方 法 オンライン(Zoom)
講 師 坂本昌代さん(都立飛鳥高校ほか講師、 認定NPO法人多文化共生センター東京)
〇第2回目 「私の都立高校での経験あれこれ! 座談会」
日 程 12月20日 (土) 10:00~12:00
対 象 第1回研修に参加された方
方 法 対面
〇イベントの詳細はこちら https://www.cinga.or.jp/7386/
6.エッセイ:崔さんのつれづれ日記(19)
紙とKindle、本のかたち
私の子供時代、本といえば、紙に文字などが印刷されたものだった。
時代劇を見るとむかしむかしは文字を書いた竹の板を紐で連ねて巻いたものだった。この竹の板本を実際見たこともなければ触ったこともないが、どこかの博物館に保管してあるなら触らせてくれるコーナーがあると嬉しい。いや貴重な歴史遺産だ、軽々に触ることはできないだろう。どこかで時代劇用小道具を触ることができるかしら?
時代は移り変わっていく。いまわたしは紙の本と電子版本(kindle)をリュックに入れて持ち歩く。
初めてkindle の存在を知った時は正直いって驚いた。まあ、すでにパソコンが普及したのだから本を読む専用パソコンみたいなものなんて容易いものでしょう。
確かにKindle は持ち運びやすい、先ほど調べたらわたしのKindleは32ギガもので,600冊の本を収納することができるそうだ。今の私のペースだと容量がいっぱいになるまえに私がoffになるでしょう。
古い人間であるわたしはまだまだ紙の本を読むほうがしっくりくる。なんで紙の本がいいのか上手く説明できないが、子供の時分からずっとお供をしてくれたからかもしれない。でも持ち歩くならKindle が便利なのも確かだ。紙の本一冊より軽いし薄い。この時代、iphone、パソコンにも慣れたからKindleの画面にも文句はない。でも習性的に紙の本を読むときは、より落ち着く気がするのだ。生まれて初めて読んだ本が紙の本だったから仕方がないでしょう。初めて触る本がkindle だったらきっと紙の本は重い、嵩張ると思うでしょうね。
次の本の形はどんなものかしら、もしかして形すらないかもしれないよね。
(NIMIC会員 崔香芸)
メール配信の申し込みは、こちらから